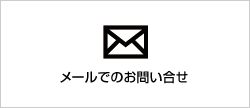令和2年度 褒賞受賞者
令和2年度 安田・阪本記念賞
- 受賞者
- 秀 道広(ひで みちひろ)先生
- 広島大学大学院 医系科学研究科 皮膚科学 教授
広島大学 副学長
- 受賞理由
-
秀 道広先生は長年にわたり蕁麻疹、アトピー性皮膚炎等の研究、診療に尽力され、その研究業績は世界の一流雑誌に論文を報告されています。
蕁麻疹の臨床,研究に関しては日本皮膚科学会 蕁麻疹ガイドラインの作成と世界的ハーモナイゼーション、蕁麻疹発症仮説と治療薬開発に貢献され、国民の健康福祉の増進に寄与されました。
また、日本皮膚科学会副理事長をはじめ、日本研究皮膚科学会理事、日本アレルギー学会理事、そして広島大学医学部長を経て、現在は副学長を務められておられます。2018年には117回日本皮膚科学会総会学術大会を主宰されるなど、安田・阪本記念賞の趣旨である研究業績はもちろん、日本の皮膚科学の発展と後進の育成に多大な貢献をされています。

- 受賞の言葉
- 第34回 安田・阪本記念賞を拝して
- 広島大学大学院 医系科学研究科 皮膚科学 秀 道広
-
この度、第34回安田・阪本記念賞受賞という、思わぬ栄光を浴することとなりました。振り返ると医学部に在籍中に縁あって実験室への出入りを始めてから38年、大学を卒業後から現在に至る研究テーマとなった蕁麻疹、アトピー性皮膚炎に取り組み始めてからも、かれこれ32年間の月日が流れました。
蕁麻疹とアトピー性皮膚炎は、いずれも我が国の初期臨床研修で経験が求められる4つの皮膚系疾患にも位置づけられるほどありふれた疾患です。しかし、教科書に書かれているアレルゲンの同定、回避が実効的な例はごく一部で、広く悪化因子として知られている感染やストレス、あるいは汗が、どのようにその病態に関わるのか、次々と現れる難治例にどう対処すれば良いのか、また、いずれもマスト細胞が関与するI型アレルギーによると考えられるのになぜ両者は目に見える症状が異なるのか、など、多くの疑問が残されています。当時、これらの疑問が正面から取り上げられることは少なく、研究を始めた頃の私には遠くに聳える絶壁を登ることはもちろん、今居る地点から前に進んでいるのかすら分からない状態でした。
一方、1980年代の終わりは医学研究に分子生物学が押し寄せてきた時代で、皮膚科では水疱症や角化症、乾癬の領域で次々と新しい研究の成果が報告されていました。その様な中、私は当時主任教授であった山本昇壯先生のご指導で、アメリカはNIH、続いてロンドンはSt Thomas’s Hospitalに留学の機会をいただき、マスト細胞の細胞内情報伝達の解明、慢性蕁麻疹における抗IgEおよび抗IgE受容体自己抗体の発見という幸運に恵まれました。その後、1996年に大学に戻ってからはマスト細胞と神経ペプチド、アトピー性皮膚炎における汗アレルギーの研究、慢性蕁麻疹における血液凝固反応の関与等の研究を続けて今日に至ります。その間、長い間地味で光りの当たりにくい研究を続けてきたように思います。しかし、多くの、そして色々な人たちとの出会いがあり、蕁麻疹への取り組みは遺伝性血管性浮腫という稀少疾患へも発展し、患者会や厚労省との関わりの機会が増え、国内外のガイドラインの作成にも携わらせていただきました。しかし、それらの活動の一つひとつは決して華々しいものではなく、また、自分自身がそれらの活動について表彰いただく機会はほとんどありませんでした。そのため、このたびの安田・阪本記念賞は大変大きな光栄です。
臨床医学の中でも、皮膚科学は特に臨床と基礎の距離が短く、診療で得た疑問、違和感、気づきを研究に反映し、また、研究の成果を自ら臨床で検証できるという素晴らしい学問領域と思います。また、近年の交通とインターネットの発達により、たとえ身近には多くの仲間が居なくても、世界中に知己を得て活動を広げることができるようになりました。このたびの受賞は、それらの仲間たち、そして私の活動を日々支えてくれた教室、研究室のメンバー、スタッフ仲間たちあってこそ実現したもので、評価委員の先生方にはもちろん、彼らに対しても深く感謝して受賞のお礼といたします。
- ご略歴
-
1984年 広島大学医学部卒業 1988年 広島大学医学系研究科(博士課程)修了、米国NIH(NHLBI)研究員 1990年 英国ロンドン大学St Thomas's Hospital研究員 1993年 厚生連尾道総合病院皮膚科部長 1996年 広島大学医学部皮膚科助手 1999年 同 講師 2001年 同 教授 2002年
-2016年,
2020年広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所副所長(兼任) 2016年 広島大学医学部長 2020年 広島大学副学長
- 学会・役職
-
- 日本皮膚科学会(専門指導医、理事・副理事長)
- 日本アレルギー学会(専門指導医、常務理事)
- 日本皮膚免疫アレルギー学会(評議員、平成24-令和2(2012-2020)年理事)
- 日本小児皮膚科学会(運営委員、平成20-令和元(2008-2019)年まで副会長)
- 日本研究皮膚科学会(評議員、平成24-29(2012-2017)年理事、平成29-令和元(2017-2019)年監事
- 日本臨床皮膚科医会
- 日本再生医療学会
- 日本褥瘡学会など
- 日本皮膚科学会、日本アレルギー学会によるアトピー性皮膚炎診療ガイドライン作成委員、蕁麻疹診療ガイドライン作成委員長
- 欧州アレルギー臨床免疫学会/EU国際アレルギー喘息ネットワーク/欧州皮膚科フォーラム/世界アレルギー機構による蕁麻疹国際ガイドライン作成委員(2013年版、2017年版、2020年版)
- 世界アレルギー機構(WAO)/欧州アレルギー臨床免疫学会による遺伝性血管性浮腫ガイドラインガイドライン作成委員(2017年版、2020年版)
- 厚生労働省薬事・食品衛生審議会(現:特立行政法人医薬品医療機器総合機構)専門委員(平成15年~)
- 広島県地域対策協議会理事(平成14年~)平成28年4月より常任理事)
- 核戦争防止国際医師会議(IPPNW)日本支部広島県支部副支部長(平成28年~令和2年)
- 受賞歴
-
2005年 第35回日本皮膚アレルギー学会総会 展示発表優秀賞 2015年 第14回 広島学長表彰 2019年 第17回 広島学長表彰
令和2年度 小川秀興賞
- 受賞者
- 佐野 栄紀(さの しげとし)先生
- 高知大学医学部 皮膚科学講座 教授
- 受賞理由
-
佐野 栄紀先生は皮膚炎症性疾患の分子機序の解明及び、乾癬のモデルマウスをはじめとして、多くの角化細胞に関する研究があり、その研究業績は国際的に高く評価されています。
また、日本研究皮膚科学会学術大会はじめ多くの皮膚科関連学会を主宰され皮膚科学研究の発展と後進の育成に寄与されました。

- 受賞の言葉
- 受賞のことば
- 高知大学医学部 皮膚科学講座 佐野 栄紀
-
このたびは、栄誉ある第5回「小川秀興賞」を頂戴し誠に光栄至極です。過去受賞された錚々たる先生方に引き続き、身の引き締まる思いです。
私は昭和58年愛媛大学を卒業後、当時父の主幹する大阪大学皮膚科に入局しました。しかし、科学的理論より経験則のみを重んじると思っていた(誤解ですが)皮膚科診療には興味がわかなかったことより、当時では新進の分野であった免疫学の泰斗であられた濱岡利之先生の教室で研究三昧の生活を送りました。ここで博士号を取らせて頂いたあと留学先までお世話になりました。3年余後、市中病院に勤務したのち吉川先生が教授であられた大阪大学に戻り、初めて皮膚科分野の研究をスタートいたしました。そこで開始した角化細胞の仕事は、竹田潤二先生、板見智先生のご指導あればこそでありました。1997年当時、竹田研はCre-loxPシステムを用いた遺伝子改変のメッカであり、その実germline KOで致死的な遺伝子を片っ端からKeratin 5依存性に破壊してその形質を調べ、のち分子機構を明らかにするreverse geneticでした。まさに博打のような仕事でしたが、誰もまだ知らない新規の発見が続き、連日午前2時3時まで興奮して過ごした幸せな数年間でした。この間、Stat3, gp130, p38α, Bcl-xLなどの角化細胞における機能を明らかにしましたが、残念ながらすべてが論文になったわけではありません。しかし、Stat3については表皮の創傷治癒・毛包成長に必須の転写因子であることを明らかに出来(EMBO J, 1999)その後、発癌にもessentialに関与することもわかり(JCI, Cancer Res, 2004), 2回目の留学先であるテキサスMDアンダーソン研究所で、活性型Stat3トランスジェニックマウスが偶然にも角化性紅斑を発症したときは(Nat Med, 2005)、ぼんやりと、これからは乾癬で食ってゆけるなぁと想像したものです。事実、このマウスを用いた乾癬モデルは理路整然とした病態理論を構築でき、その後Th17が角化細胞のStat3を活性化することが明らかになったことで、東西から掘り進んだトンネルが真ん中で出会うように乾癬の表皮-免疫軸サーキットが完成しました。
2007年高知大皮膚科学教室を任されて以来、現在まで多くのマウスモデルで仕事をしてきました。もちろんこのStat3トランスジェニックも、バイオの効果判定や新規治療法開発に大活躍をしました。これらの業績は、地方大学の限られたメンバーでありながら私とともに汗を流してくれる仲間の努力によります。また、大阪大学時代から引き続いて、多くの恩師、メンター、仲間が遠くから我々を支えて頂いたお陰と感謝に堪えません。「小川秀興賞」はこれら皆さんとともに与えられた受賞と思います。この度は誠にありがとうございました。
- ご略歴
-
1983年 愛媛大学医学部卒業 1983年 医員(研修医)(大阪大学医学部附属病院皮膚科) 1984年 大阪大学大学院医学系研究科入学 1988年 大阪大学大学院医学系研究科博士課程修了 1988年 研究生(大阪大学医学部皮膚科学講座) 1988年 医員(大阪大学医学部附属病院皮膚科) 1988年 Research fellow(USA, Albert Einstein Medical College免疫微生物学) 1992年 市立堺病院皮膚科医長 1994年 大阪大学助手医学部皮膚科学講座 1999年 大阪大学講師大学院医学系研究科(皮膚科学講座) 2003年 Assistant professor(USA, MD Anderson Cancer Center) 2004年 財団法人住友病院皮膚科部長(平成17年10月まで) 2005年 大阪大学講師大学院医学研究科(皮膚科学) 2006年 大阪大学助教授大学院医学研究科(皮膚科学) 2007年 高知大学医学部皮膚科学講座教授 2017年 高知大学免疫難病センター副センター長
- 学会・役職
-
- 日本皮膚科学会
- 日本研究皮膚科学会(2011-13 学術委員長)
- 日本皮膚免疫アレルギー学会(2019より理事長)
- 日本皮膚悪性腫瘍学会理事
- 日本乾癬学会理事
- 日本免疫学会 科学コミュニケーション委員会委員
- 日本分子生物学会
- 日本色素細胞学会
- 日本白斑学会
- 日本アレルギー学会
- 日本リウマチ学会
- Journal of Dermatology, Section Editor
- 受賞歴
-
2000年 日本皮膚科学会賞(皆見賞) 2001年 ガルデルマ賞受賞 2004年 大阪大学皮膚科同窓会賞 2005年 Eugene Farber賞(米国乾癬研究賞) 2006年 日本研究皮膚学会賞 2008年 加齢皮膚医学研究基金「ロート賞」 2009年 Annual ESDR meeting, Poster Award
令和2年度 清寺眞記念賞
- 受賞者
- 若松 一雅(わかまつ かずまさ)先生
- 藤田医科大学医療科学部 名誉教授
- 受賞理由
-
若松一雅先生はメラニン合成及びメラナイゼーション機構の化学的解明を長年、伊藤祥輔先生と共同研究され多くの優れた研究業績を報告されています。
メラニン測定ではお二人の測定法が世界標準となり、世界中のメラニン研究の発展に貢献されています。
また、最近では化石からのメラニン抽出と解析の仕事がNature誌に掲載されるなど、メラニン研究におけるお二人の存在はバイブル的であり、歴史ある清寺 眞記念賞をお受けいただくに相応しい業績を残されています。

- 受賞の言葉
- 受賞の言葉
- 藤田医科大学 若松 一雅
-
この度、栄えある2020年度 (令和2年) 第20回「清寺 眞記念賞」を受賞することになりました。とても栄誉のことであり、感謝と御礼の言葉を申し述べます。
故清寺 眞先生は、melanosomeを発見したことでよく知られており、ご自身の研究テーマである色素細胞の研究を発展させ、数多くの国際的な研究会・学会を主催されました。また、現在の日本色素細胞学会の前身と考えてもよいPigment Cell Clubを主宰されました。奇しくも私は、昨年度まで日本色素細胞学会および国際色素細胞学会 (IFPCS) の理事であり、八年前に日本色素細胞学会事務局長とその後、会長を歴任しましたので、歴代の受賞者の方々のお名前をよく存じ上げております。それぞれ第一線で第一級の業績を上げられた受賞者の先生方の中に自分の名前を加えさせていただくことは、大変光栄なことと存じます。
私は、名古屋大学理学部におりました時に、共同受賞者である伊藤祥輔先生のお力添えで、藤田保健衛生大学衛生学部(当時)の化学教室に就職いたしました。伊藤先生が、丁度、当時メラニン研究を始められて軌道に乗っていた頃であり、私は、メラニンについて最初から先生の下で勉強を始めました。メラニンは、アミノ酸チロシンがチロシナーゼ酸化されて生成する黒色〜褐色色素のユーメラニンと黄色〜赤色色素のフェオメラニンが複雑に共重合した高分子化合物です。この化合物の物質量を測定するためには、メラニンの化学的分解法の開発が必須でした。新たに開発した微量メラニン定量法は、現在では、メラニンの構造を研究する上で最も有効な手段の一つになり、この化学的微量分解法を用いて、今までにヒト、マウス、鳥類などの脊椎動物の体毛、羽根毛、皮膚、培養細胞など、また中脳黒質に存在するニューロメラニンの定量までその分析の範囲は発展しました。また、メラノジェネシスの解明を我々が得意とする化学的手法を用いて貢献しました。最近では、化粧品による白斑の原因の解明や化石中のメラニン色素の構造研究まで広がりをみせ、幸いにも一流の欧文誌に掲載されるまでになりました。これらの幅広いメラニン研究は、我々のメラニンの微量分析法が世界中の研究者に採用されたことにより、この分析方法が、メラニンの定量に最も優れた方法の一つであることを認知されたことに他なりません。
この度、藤田医科大学内にメラニン化学研究所を設立しました。所長として、さらに他施設の研究者との共同研究を推進し、同時にメラニン色素の化学的役割の未知なる分野の解明を進めるようこれからも研究を続ける所存であります。
終わりに、今後の貴財団の更なるご発展を祈念致します。
- ご略歴
-
1977年 名古屋大学理学部化学科卒業 1977年 名古屋大学大学院理学研究科前期課程入学 1979年 名古屋大学大学院理学研究科前期課程修了 1979年 愛知医科大学化学教室助手 1981年 名古屋大学大学院理学研究科大学院研究生 1986年 理学博士(名古屋大学第470号) 1986年 藤田学園保健衛生大学医学部客員講師「化学」 1987年 藤田学園保健衛生大学衛生学部助手「化学」 1988年 藤田学園保健衛生大学衛生学部講師「化学」 1995年 医学博士(藤田保健衛生大学第229号) 1995年 英国ニューキャッスル大学医学部皮膚科学教室留学 1996年 藤田保健衛生大学衛生学部助教授 1998年 ESPCR Travel Stipend Awardee 2003年 藤田保健衛生大学衛生学部教授「化学」 2003年 藤田保健衛生大学大学院保健学研究科臨床検査学領域(修士課程)教授 2014年 藤田保健衛生大学大学院保健学研究科生体情報検査科学分野(博士後期課程)教授 2017年 藤田保健衛生大学医療科学部特任教授 2017年 Takeuchi Medal(国際色素細胞学会学術賞)受賞 2019年 藤田医科大学医療科学部退職
- 学会・役職
-
- 国際色素細胞学会(IFPCS)理事(2014-2020)
- 日本色素細胞学会 評議員(1995-)、理事(2001-2006、2008-2020)
- 日本色素細胞学会事務局長(2012-2015)、日本色素細胞学会会長(2015-2018)
- 受賞歴
-
2017年 国際色素細胞学会連合(IFPCS)Takeuchi Medal 2018年 公益財団法人 コーセーコスメトロジー研究振興財団研究助成
令和2年度 清寺眞記念賞
- 受賞者
- 伊藤 祥輔(いとう しょうすけ)先生
- 藤田医科大学医療科学部 名誉教授
- 受賞理由
-
伊藤祥輔先生はメラニン合成及びメラナイゼーション機構の化学的解明を長年、若松先生と共同研究され多くの優れた研究業績を報告されています。
メラニン測定ではお二人の測定法が世界標準となり、世界中のメラニン研究の発展に貢献されています。
また、最近では化石からのメラニン抽出と解析の仕事がNature誌に掲載されるなど、メラニン研究におけるお二人の存在はバイブル的であり、歴史ある清寺眞記念賞をお受けいただくに相応しい業績を残されています。

- 受賞の言葉
- 受賞のことば
- 藤田医科大学 伊藤 祥輔
-
この度は、歴史と栄誉ある「清寺眞記念賞」を受賞することになり、大変光栄に思うと同時に、いささかの驚きを禁じ得ません。定年退職後11年目を迎え、75歳となった私にとって、縁のない賞と思っていたからです。また、30年来の共同研究者である若松一雅名誉教授との共同受賞についても、本賞の歴史のなかで前例のないことであり、嬉しさも倍増しております。また、清寺眞先生とは、先生が1980年に第11回国際色素細胞会議を仙台で主催された際にお目にかかっており、また、私が2017年に米国デンバーにおいて開催された第23回国際色素細胞会議において、「Seiji Memorial Lecture」を講演するなど、ご縁を感じている次第です。
振り返ってみれば、1977年に藤田医科大学(当時は名古屋保健衛生大学)に職を得て以来、留学中にテキサス大学海洋科学研究所、ナポリ海洋生物学研究所で遭遇したメラニン研究を継続、発展させたいと願って、今日に至っております。特に、臨床検査技師を養成する教育にも従事し、生化学的な分析法をいかに精度よく、かつ微量化、簡便化するかに腐心してきました。それが結実したのが、1985年に発表した、高速液体クロマトグラフィーを用いるユーメラニンとフェオメラニンの微量定量法であります。この分析法はその後も改良を重ね、より広範に利用されるに至りました。この方法は、若松教授と共にメラノジェネシスの化学的研究に適用しておりますが、幸いなことに、国の内外から皮膚科学、遺伝学、細胞生物学など、多岐にわたる分野の研究者から共同研究の提案をいただき、長年にわたって成果を挙げ続けることができました。
受賞は、定年後、現役時代には時間的な制約のなかで困難であった、自分自身で立案し、実験し、論文執筆するという、自己完結型の研究を生き甲斐として精進してきた結果と喜んでおります。特に、「紫外線によるメラニン構造の修飾」、「フェノール類のメラノサイトに対する細胞毒性の機序」、「化石メラニンの化学的同定」は、主に定年退職後に着手した研究であり、長年にわたるメラニン研究の経験が大いに役立ちました。今後も、今回の受賞を励みに、気力、体力、知力が許す限り、「生涯一研究者」を目指して、引き続き精進して参りたいと願っております。
- ご略歴
-
1967年 大阪大学理学部化学科卒業 1969年 大阪大学大学院理学研究科修士課程修了 1972年 名古屋大学大学院理学研究科博士課程修了 1972年 理学博士の学位授与(名古屋大学) 1972年 名古屋大学理学部助手 1972年 米国テキサス大学海洋科学研究所博士研究員 1975年 イタリア・ナポリ海洋生物学研究所客員研究員 1977年 名古屋保健衛生大学生薬研究塾主任研究員 1978年 藤田学園保健衛生大学衛生学部講師「化学」 1983年 医学博士の学位授与(名古屋保健衛生大学) 1983年 名古屋保健衛生大学医学部助教授(化学) 1985年 藤田保健衛生大学衛生学部教授(化学) 1989年 カナダ・アルバータ大学医学部客員教授(皮膚科学:4カ月間) 2005年 藤田保健衛生大学衛生学部長 2006年 学校法人藤田学園 理事 2010年 藤田保健衛生大学(現 藤田医科大学) 名誉教授
- 学会・役職
-
- 日本色素細胞学会(1987-2006、2009-2018 理事)
- 国際色素細胞学会(理事1993-2005、1993-96事務局長、1999-2002 理事長)
- 第8回日本色素細胞学会年次学術大会 会頭(1993年12月10日〜11日)
- 第17回国際色素細胞会議 会頭(1999年10月30日〜11月3日)
- Pigment Cell Research(現Pigment Cell & Melanoma Research)Editorial Board (1987-), Executive Editor (2007-2009)
- Melanoma Research, Editorial Advisory Board (1991-2015)
- 受賞歴
-
1983年 坂幹雄賞(藤田学園医学・保健衛生学研究奨励金)受賞 1999年 Myron Gordon Award(国際色素細胞学会学術賞)受賞 2002年 ヨーロッパ色素細胞学会名誉会員 2005年 The Henry Stanley Raper Medal(国際色素細胞学会生化学部門学術賞)受賞 2017年 Seiji Memorial Lectureship(国際色素細胞学会記念講演)
褒賞・外国人留学生奨学金
お問い合わせ
TEL 06-6376-5590
FAX 06-6376-5625