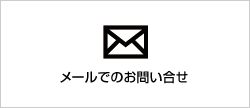令和7年度 褒賞受賞者
褒賞の設立趣旨、褒賞対象者は、各褒賞のページをご覧ください。
令和7年度 安田・阪本記念賞
- 受賞者
- 藤本 学(ふじもと まなぶ)先生
- 大阪大学大学院医学系研究科皮膚科学 教授
- 受賞理由
-
藤本学博士は、強皮症や皮膚筋炎をはじめとした膠原病、免疫疾患の病態解明と治療法の確立に取り組まれ、特に皮膚筋炎に関するご研究では、特異的自己抗体、特に抗TIF1抗体のサブセット分類に関する先駆的な研究成果を発表されるなど、極めて重要な研究業績を上げられています。
また、藤本博士はInternational League of Dermatology Society(ILDS)理事、日本研究皮膚科学会 理事長、日本皮膚科学会 理事長をお務めになられるなど、国内外における皮膚科学会の発展に多大なる貢献をされています。

- 受賞のことば
- 大阪大学大学院医学系研究科 皮膚科学 教授
大阪大学 免疫学フロンティア研究センター 皮膚免疫学 教授
藤本 学 -
このたび、第39回安田・阪本記念賞という栄誉ある賞を賜ることとなり、身に余る光栄に存じます。リディアオリリー記念ピアス皮膚科学振興財団の小川秀興理事長をはじめ、財団関係者の皆様、そして選考委員会の皆様に、心より御礼申し上げます。
私のような、まだ道半ばの立場にある者が、このような由緒ある賞を頂けることは、たいへんうれしく、また驚きでもありますのと同時に、今後さらに精進を重ねるようにとの叱咤激励と受け止め、身の引き締まる思いでおります。これまでの歩みが少しでも評価いただけたことを励みに、今後も一層責任をもって皮膚科学の発展に寄与してまいりたいと存じます。
私は1992年、石橋康正先生が教授を主宰されていた東京大学皮膚科学教室に入局し、当時強皮症グループの責任者であられた竹原和彦先生(金沢大学名誉教授)のご指導のもと、膠原病診療の手ほどきを受けました。その後も、全身性強皮症や皮膚筋炎をはじめとする膠原病、さらには自己免疫や自己抗体に関する研究に継続して取り組んでまいりました。
なかでも、患者さん方から学ばせていただいたことの多さは計り知れません。若い頃、患者さんから寄せられた問いや願いが、私にとっての「宿題」となり、元来怠け者である私のドライビングフォースとなってきたように思います。研究面では、佐藤伸一先生(東京大学教授)より多くのご指導をいただきました。また、留学先のDuke大学免疫学教室のThomas Tedder教授には、B細胞の研究にとどまらず、人生の指針ともなる多くのご指導をいただき、今なお深く感謝しております。
2000年代後半には、ちょうど皮膚筋炎における疾患特異的自己抗体の研究が急速に進展していた時期に立ち会い、その最前線で仕事ができたことは、私のキャリアにおける大きな転機であり、かけがえのない経験となりました。膠原病は他科との連携を要する領域であり、その中で皮膚科ならではの視点や強みを発信し続けることが、私のひとつの使命であると感じております。近年は思いがけず、International League of Dermatological Societies(ILDS)のRegional Directorや、日本皮膚科学会の理事長を拝命する機会をいただき、日本の皮膚科学の将来や国際的な連携や貢献についても深く考える責任を実感するようになりました。今後は、こうした領域にも積極的に関与してまいりたいと考えております。
これまで、東京大学、金沢大学、筑波大学、そして大阪大学の皮膚科学教室に所属させていただきました。それぞれの教室や同窓会における多くの先生方にご指導をいただき、また同僚やスタッフの皆様とともに仕事ができたことは、私にとって何よりの財産です。そして、常に新しい視点とエネルギーを与えてくれる若手の先生方の存在も、私の原動力となっております。このたびの受賞を励みに、今後も一歩一歩着実に頑張ってまいりたいと思います。誠にありがとうございました。
- ご略歴
-
1992年 東京大学医学部医学科 卒業 1994年 東京大学医学部 皮膚科 助手 1997年 米国 Duke大学メディカルセンター免疫学 研究院 2000年 国立国際医療センター研究所 細胞修飾生体反応研究室長 2001年 博士(医学)(東京大学) 2004年 東京大学医学部付属病院 皮膚科 特任講師 2005年 金沢大学大学院医学系研究科 皮膚科学 助教授(准教授に名称変更) 2013年 筑波大学 医学医療系 皮膚科学 教授 2019年 大阪大学大学院医学系研究科 皮膚科学 教授 2019年 大阪大学 免疫学フロンティア研究センター 皮膚免疫学 教授(併任)
- 所属学会・役職
-
- 日本皮膚科学会 理事長(2024年-)
- 日本研究皮膚科学会 理事長(2023年-2025年)
- International League of Dermatological Societies, Regional director
- 日本皮膚免疫アレルギー学会 理事
- 日本乾癬学会 理事
- 日本医学会 評議員
- 日本免疫学会 評議員
- 日本臨床免疫学会 代議員
- 受賞歴
-
2009年 Rhoto Dermatology Investigator Award(ロート製薬) 2013年 JSID Award(日本研究皮膚科学会) 2015年 Rising Star Award(ポーラ化粧品/日本皮膚科学会)
令和7年度 清寺眞記念賞
- 受賞者
- 奥山 隆平(おくやま りゅうへい)先生
- 信州大学医学部皮膚科学教室 教授
- 受賞理由
-
奥山隆平博士は、悪性黒色腫(メラノーマ)の治療法として、IL-12を発現するがん治療用ウイルスを用いたウイルス免疫療法や、メラノーマ患者の血液循環腫瘍由来RNAを用い病勢をモニタリングする新規検査法の開発において卓越した業績を上げられています。
また、奥山博士は、第83回日本皮膚科学会東京東部支部学術大会、第37回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会、第125回日本皮膚科学会総会を主催されるなど、皮膚科学の発展に多大なる貢献をされています。

- 受賞のことば
- 信州大学医学部皮膚科学教室 教授
奥山 隆平 -
このたびは、「清寺眞記念賞」という栄誉ある賞を賜り、誠に光栄に存じます。本邦はじめ世界の皮膚科学の発展に多大なる貢献をなされ、多くの優れた後進を育てられた清寺眞先生のお名前を冠した本賞を拝受いたしましたことは、身に余る光栄であると同時に、その重責を真摯に受け止めております。
今回の受賞に際し、これまで私の学術的歩みにご指導・ご助言を賜りましたすべての先生方に、心より御礼申し上げます。とりわけ、東北大学皮膚科学教室在籍中に格別のご高配を賜りました田上八朗先生(東北大学名誉教授)には、皮膚科学に対する深遠な学識と高い倫理観、そして研究と診療に臨む真摯な姿勢を教えていただきました。田上教授のもとで過ごした日々は、私の臨床医ならびに研究者としての礎となっており、今日に至るまで常に私の行動指針となっております。併せて、同教室においてご指導くださいました諸先生方に、改めて深甚なる感謝の意を表する次第です。
また、信州大学皮膚科学教室における日々の活動においては、教室スタッフならびに大学院生、地域医療に従事されている多くの医療関係者の皆様のお力添えに支えられております。皮膚疾患の病態解明に資する研究、ならびに個別化医療の実現に向けた取り組みを継続できておりますのは、ひとえに関係者のご協力とご理解の賜物であり、ここに深く感謝申し上げます。
さらに、本賞をお授けくださった財団法人リディアオリリー記念ピアス皮膚科学振興財団の皆様、ならびに理事長をお務めの小川秀興先生に対し、心より感謝申し上げます。小川理事長におかれましては、長年にわたり皮膚科学の振興にご尽力されるとともに、若手研究者の育成にも惜しみないご支援を賜っておりますことに、深甚なる敬意を表します。このたびの受賞を励みとし、より一層精進を重ねてまいります所存でございます。
最後になりますが、日頃より私の活動を支えてくれている皆様に深く感謝申し上げます。今後とも、皮膚科学の進歩と社会への貢献を目指し、臨床・研究・教育に誠心誠意取り組んでまいる所存でございます。
このたびは誠にありがとうございました。
- ご略歴
-
1989年 東北大学 皮膚科入局 1995年 東北大学大学院医学系研究科 卒業 1992年 福島県磐城共立病院 皮膚科 1997年 Massachusetts General Hospital/Harvard Medical School, Research fellow 2000年 東北大学医学部附属病院 助手 2003年 東北大学医学部附属病院 講師 2005年 東北大学医学部 助教授 2007年 東北大学医学部 准教授 2010年 信州大学医学部 皮膚科 教授 2023年 信州大学医学部 学部長
- 学会・役職
-
- 日本皮膚科学会 副理事長
- 日本研究皮膚科学会 評議員
- 日本乾癬学会 理事
- 日本癌学会 代議員
- 日本皮膚免疫アレルギー学会 代議員
- 日本皮膚悪性腫瘍学会 理事長
- 主な主催学会
-
2019年 第83回日本皮膚科学会東京東部支部学術大会 2021年 第37回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会 2026年 第125回日本皮膚科学会総会
令和7年度 小川秀興賞
令和7年度 小川秀興賞は、お二人の先生が受賞されました
- 受賞者
- 久保 亮治(くぼ あきはる)先生
- 神戸大学大学院医学研究科内科系講座 皮膚科学分野 教授
- 受賞理由
-
久保亮治博士は、細胞生物学、形態学、質量分析顕微鏡などを駆使され、皮膚バリア機構の解析やアトピー性皮膚炎の病態解明を行われるとともに、汗孔角化症の原因遺伝子の特定、遺伝性魚鱗癬の病態解明を行われ、「細胞競合モザイク疾患」という概念を提唱されるなど、多岐にわたる成果を上げられています。
また、久保博士は、日本フォトダーマトロジー学会 第7回学術大会を主催された他、日本皮膚科学会 代議員や日本研究皮膚科学会 評議員をお務めになり、学会活動でも重要な役割を果たされています。
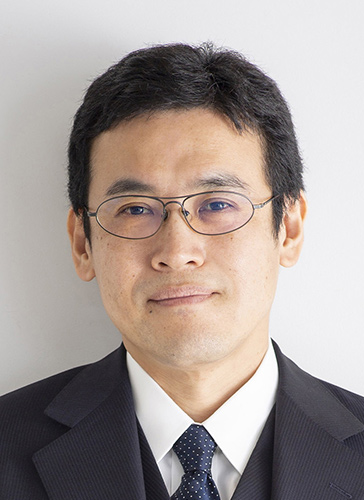
- 受賞のことば
- 神戸大学大学院医学研究科内科系講座 皮膚科学分野 教授
久保 亮治 -
この度は、「小川秀興賞」という名誉ある賞の受賞者に選考していただき、リディアオリリー記念ピアス皮膚科学振興財団小川理事長をはじめ財団関係者の皆様、選考委員会の皆様に心より感謝申し上げます。
私は大阪大学皮膚科にて研修を始めた年に、栄養障害型表皮水疱症の3名の患者さんと出会いました。橋本公二先生(当時は大阪大学皮膚科助教授)の指導のもと、患者さんから樹立した培養表皮シートを貼付する臨床研究に携わる経験を持ち、細胞接着と遺伝性疾患という、その後の私の人生に深く関わる分野に惹きつけられました。その症例の学会発表を通じて、慶應義塾大学の天谷雅行先生、弘前大学の玉井克人先生と出会いました。弘前大学の橋本功先生の御好意で、弘前大学に1ヶ月間泊めていただき、上記の患者さんの遺伝子診断を玉井先生の指導で行ったのが、私の分子生物学の事始めでした。その後、橋本公二先生、天谷雅行先生に推薦いただき、本当に何でも自由にさせて下さった吉川邦彦教授に送り出されて、京都大学の分子細胞情報学講座の故・月田承一郎先生のもとに国内留学し、大学院の4年間とポスドク/助教の6年間、合わせて10年を京都大学にて過ごしました。中心体や微小管、繊毛の研究に携わり、繊毛の先端に局在する新規蛋白を発見して「Sentan」と命名し、新しい蛋白を見つけて日本語の名前を付けたいという、昔からの夢の1つを叶えることができました。
当時の月田研ではタイトジャンクションの研究が主流で、オクルディン、クローディンという接着分子が次々と発見され解析されていくところを一緒に経験することができました。しかし月田先生が残念ながら早世されてしまい、私は皮膚科に戻ってclinician scientistとして出直すことにしました。そんな私を受け入れて下さったのが、慶應義塾大学皮膚科で教授になられたばかりの天谷先生、そして准教授の石河晃先生ら、慶應皮膚科の皆様でした。慶應皮膚科で10年ぶりに皮膚科臨床を再開するとともに、新しい研究テーマとして皮膚のバリア機構の解析を始めました。フィラグリンKOマウスの樹立、タイトジャンクションバリアとのドッキングを介したランゲルハンス細胞による体外抗原の取得機構、顆粒層細胞の扁平ケルビン14面体形状を利用したタイトジャンクションバリアを保ちつつ細胞がターンオーバーするメカニズム、質量分析顕微鏡を用いた天然保湿因子の角層内分布の可視化といった成果をあげることができ、「久保は重層上皮の細胞生物学をやりなさい」という月田先生の宿題に答えることができたのかなと感じています。
また、大阪大学時代に表皮水疱症に出会ってから、遺伝性疾患の新しい原因遺伝子を発見することが自分のもう1つの夢になっていました。遺伝性疾患を石河先生のもとについて学びつつ、次世代シーケンサを用いた解析体制を整え、長島型掌蹠角化症の原因遺伝子SERPINB7、汗孔角化症の新しい原因遺伝子FDFT1の発見といった成果をあげることができました。不思議な縁といいますか、ここでも重層上皮と角化が表現型に関わる疾患と深く関わっています。遺伝学的解析は、とてもここには書き切れないほど様々な方々との共同研究で進めてきました。なかでも、国立成育医療研究センターの中林一彦先生、慶應義塾大学臨床遺伝学センターの小崎健次郎先生、鈴木寿人先生、百寿総合研究センターの佐々木貴史先生らの助けがなければ、何一つ成し遂げられなかったと思います。みなさまに心から感謝しています。
しかし、今までの人生で誰の助けが一番大きかったかと言えば、それは妻から受けたサポートで間違いありません。京都大学の月田研で出会ってすぐに結婚し、私が慶應に移れば、三菱化学生命科学研究所、慶應の医化学講座と渡り歩き、現在は神戸大学皮膚科にて遂に同じ職場で一緒に働いています。質量分析イメージングという妻自身の研究テーマを進める傍ら、神戸大学皮膚科の大学院生たちの研究指導を行ってくれています。心から感謝しています。
今日まで健康に、充実した人生を送ることができ、このような名誉ある賞の受賞者に選考されましたのは、ご指導をいただいた先生方、研究にご協力いただいた様々な研究者や患者と御家族の皆様、私と一緒に疾病と戦ってくれる神戸大学と慶應義塾大学の教室員とそれを支えて下さる技術員や秘書の皆様、そしていつもサポートしてくれる家族のお蔭と感謝しています。私にはもう1つ夢が残っています。いつか新しい治療法を見出したいという夢です。本賞の受賞者の名に恥じないように、これからも夢に向けて、全力で走り続けたいと思います。ありがとうございました。
- ご略歴
-
1994年 大阪大学医学部 卒業 1994年 大阪大学医学部皮膚科学教室 医員(研修医) 1995年 大阪労災病院 研修医 2000年 博士(医学)(大阪大学) 2000年 科学技術振興事業団 月田細胞軸プロジェクト 研究院 2001年 京都大学大学院医学研究科 分子細胞情報学講座 助手 2006年 慶應義塾大学医学部 皮膚科学教室 助教 2008年 慶應義塾大学医学部 総合医科学研究センター 特任講師 2013年 慶應義塾大学医学部 皮膚科学教室 専任講師 2016年 慶應義塾大学医学部 皮膚科学教室 准教授 2021年 神戸大学大学院医学研究科内科系講座 皮膚科学分野 教授
- 学会・役職
-
- 日本研究皮膚科学会(事務総長)
- 日本皮膚科学会(中部支部代議員)
- 日本乾癬学会(代議員)
- 日本小児皮膚科学会(運営委員)
- 日本皮膚免疫アレルギー学会(代議員)
- 日本フォトダーマトロジー学会(理事)
- 皮膚かたち研究学会(理事)
- 日本炎症・再生医学会
- 日本細胞生物学会
- 日本色素細胞学会
- 日本人類遺伝学会
- 日本白斑学会
- 日本分子生物学会
- 日本臨床皮膚科医会
- 日本レーザー医学会
- The American Society of Human Genetics
- Society for Investigative Dermatology
- 受賞歴
-
2010年 日本研究皮膚科学会 JSID's Fellowship SHISEIDO Award 2010年 日本皮膚科学会 皆見省吾記念賞 2015年 坂口光弘記念慶應義塾医学振興基金 慶應医学賞研究奨励賞受賞 2018年 日本研究皮膚科学会JSID賞 2018年 慶應医学会 野村達次賞 2019年 マルホ・高木皮膚科学振興財団 マルホ・高木賞 2020年 慶應義塾大学医学部三四会 北里賞
- 主な主催学会
-
2024年 日本フォトダーマトロジー学会 第7回学術大会 会頭
令和7年度 小川秀興賞
令和7年度 小川秀興賞は、お二人の先生が受賞されました
- 受賞者
- 高橋 健造(たかはし けんぞう)先生
- 琉球大学大学院医学研究科 皮膚科学講座 教授
- 受賞理由
-
高橋健造博士は、皮膚の創傷治癒や角化機構に関する研究、遺伝性角化症の病態解明や治療法の開発において国際レベルで評価される業績を上げられた他、沖縄・琉球諸島に固有の皮膚疾患にも着目され、疫学調査や病態解明、治療にも取り組まれるなど、沖縄地方の公衆衛生学的な課題の解決にも深く貢献されています。
また、高橋博士は、第75回日本皮膚科学会西部支部学術大会、第50回皮膚かたち研究学会学術大会 会長を主催されるなど、学会活動も活発に展開されています。

- 受賞のことば
- 琉球大学大学院医学研究科 皮膚科学講座 教授
高橋 健造 -
この度、全く思いもかけずに令和7年度の小川秀興賞へ選出していただき、小川理事長をはじめ財団や選考委員会の皆様、これまでの京都大学・群馬大学・琉球大学でご一緒した先達や同僚や大学院生達、留学先のピエール・クーロン博士に心より感謝を申し上げます。私自身も大変に光栄でうれしく、少々面映ゆく存じております。
この賞は、皮膚科学の中でも表皮角化細胞の動態や分化異常に係わる研究者を対象とした賞であるとお聞きしました。これまで受賞された9名の先駆者を拝見しましても、一貫された姿に正にその通りと納得する一方で、私など自分の興味に応じて好きに研究者生活を続けてきた身にとりましては、少々、面食らってもおります。
小川秀興先生、角化症、あるいはリディアオリリー記念ピアス皮膚科学振興財団と私個人の関わりと申しますといろいろ思い出されます。
私は1986年に京都大学を卒業後、88-92年に大学院生として神経伝達やシグナル伝達に関する分子単離解析を中心とする基礎医学の研究室で過ごしました。私自身が表皮の分化や多様性、創傷治癒や最近の興味である皮膚の進化に興味を持つきっかけとなったのは、1990年前後の表皮水疱症や先天性魚鱗癬の病態理解が急速に広がった時代背景があります。小川先生を含めた日本の研究者が形態学的にケラチン分子の異常を示唆し、欧米の患者さんでケラチン遺伝子の優性ネガティブ変異による疾患として理解されました。当時は一般の大学院生レベルでも自由に新規遺伝子のクローニングが可能となった時期で、その熱気の中、私と同年齢のピエール・クーロン先生のジョンス・ホプキンス大学へ93年に留学し、創傷治癒に係わるケラチン蛋白の発現調節や各ケラチン蛋白の相違に係わる研究に携わりました。帰国後の98年からは、小川先生が主催されてます東京商工会議所での角化症研究会への週末が、今も毎年真夏の楽しみであります。
ピアス皮膚科学振興財団、特にスカイクラブとして個人的にも長いお付き合いを頂いております財団の重松剛さまとは、北海道の小樽市で皮膚科クリニックを開業していた両親の時代からのお付き合いでありました。今は小田原で暮らしております母親に、今度、重松さんがいた財団より小川先生の名前の賞を頂くことになったと伝えますと、ことのほか喜んでくれました。
15年前より沖縄は琉球大学での教授職として今は主に管理職と外来診療にあたっておりますが、霊長類皮膚の観察やハンセン病・ブルリ潰瘍の研究では、琉球大学の霊長類学者や国立感染研の先生達との繋がりで、東西アフリカのケニアやコートジボアールでのフィールドでサルとヒトの創傷治癒に関する仕事にも係わることが出来ました。今後の目標や興味といたしましては、折角、沖縄の患者さんの診療で楽しい時間も持てておりますし、一世代前までの琉球諸島の課題であったハンセン病と現代沖縄の課題である頭部血管肉腫に、何らかの寄与を出来たら良いなと思っております。
末筆となりましたが、賞とともにご支援を賜りましたことを心より感謝申し上げるとともに、御財団の益々のご発展を祈念いたします。
- ご略歴
-
1986年 京都大学医学部卒業 1986年 京都大学医学部付属病院 皮膚科研修医 1987年 和歌山赤十字病院 皮膚科研修医 1988年 京都大学大学院医学研究科 博士課程内科系専攻 1992年 同 修了 1993年 米国 ジョンス・ホプキンス大学 生化学/皮膚科学教室 ポストドクトラルフェロー 1993年 博士(医学)(京都大学) 1996年 京都大学大学院医学研究科 皮膚病態学講座 助手 2001年 群馬大学医学部 皮膚科学教室 講師 2002年 京都大学大学院医学研究科 皮膚生命科学講座 講師 2010年 琉球大学医学部 皮膚病態制御学講座 准教授 2016年 琉球大学医学部 皮膚病態制御学講座 教授 2017年 琉球大学医学部 副医学部長 2021年 琉球大学医学部 医学科長 2025年 琉球大学病院 副院長(診療担当)
- 学会・役職
-
- 費用対効果評価(厚労省)
- 大学設置・学校法人審議会大学設置分科会委員長(文科省)
- 日本医療研究開発機構 医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業(2018-2022)
:アフリカにおける顧みられない熱帯病(NTDs)対策のための国際共同研究プログラム(AMED) - ハンセン病治療指針(第4版)(日本ハンセン病学会・治療指針ワーキンググループ)
- 受賞歴
-
2000年 Research Fellowship Award of Dermatology Foundation sponsored by
American Academy of Dermatology2000年 第1回 ガルデルマ賞 2002年 Albert M. Kligman Fellowship Award sponsored by
Society of Investigative Dermatology2002年 第1回 日本再生医療学会総会 優秀演題 2009年 第108回 日本皮膚科学会総会 ポスター賞 2010年 沖縄県医科学研究財団 研究奨励賞
褒賞・外国人留学生奨学金
お問い合わせ
TEL 06-6376-5590
FAX 06-6376-5625